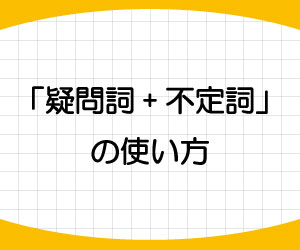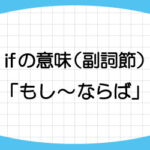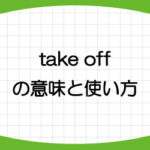疑問詞+不定詞(to+動詞の原形)の使い方は、主に2つのポイントがあります。
1つ目は、「何を~するべきか」という訳し方に特徴があることです。
2つ目は、「疑問詞+不定詞(to+動詞の原形)」を言葉のかたまりとしてとらえるということです。
今回の記事では、「what to do」「how to do」「where to do」「when to do」「which 名詞 to do」の使い方を例文で解説していきます。
what to do「何をするべきか」
I didn’t know what to say to him.
私は彼に何を言うべきか分からなかった。
what to doは「何をするべきか」という意味になります。直訳すると「何をする」になりますが、これだけでは日本語に訳した時に伝わりにくいので、疑問詞+不定詞は「何を~するべきか」と訳すことが多い。
「what + to 動詞の原形」をかたまりとして扱うのが疑問詞+不定詞の使い方です。
疑問詞+不定詞の使い方は、「何を~するべきか」という訳し方の特徴と、「疑問詞 + to 動詞の原形」をかたまりとして扱うという2つのポイントを押さえておきましょう。
Sponsored Links
例文では、what to say(何を言うべきか)という部分が疑問詞+不定詞のかたまりになっています。
I didn’t know(私は分からなかった)という内容から分かるように、この例文は過去の出来事について言っていますが、不定詞は「to+動詞の原形」になるので、what to say(何を言うべきか)のsayは、過去形ではなく動詞の原形になります。
<例文>
We didn’t know what to do.
(私たちはどうすべきか分かりませんでした。)
I told her what to see in Kyoto.
(私は彼女に京都で何を見るべきかを話しました。)
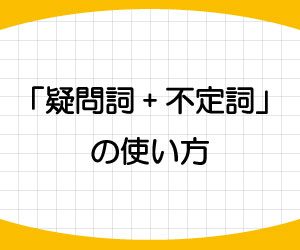
how to do「どのようにするべきか」
I didn’t know how to cook that dish.
私はその料理の作り方が分からなかった。
how to doは「どのようにするべきか」という意味になります。how to doを直訳すると「どのようにする」になりますが、これだけだと日本語訳として不十分なので「どのようにするべきか」と訳すことが多い。
特にhow to doは「~のやり方」という簡潔な訳し方で使われることがあります。
例文では、I didn’t know(私は分からなかった)という過去の出来事について言っていますが、how to cook(料理の作り方)のcookは動詞の原形になります。
疑問詞+不定詞のかたまりは、必ず「不定詞=to+動詞の原形」になるのがポイントです。
<例文>
Please tell me how to play that game.
(そのゲームの遊び方を教えてください。)
The coach taught him how to swim.
(コーチは彼に泳ぎ方を教えた。)
Sponsored Links
where to do「どこでするべきか」
I didn’t know where to buy the ticket.
私は切符をどこで買うべきか分からなかった。
where to doは「どこでするべきか」という意味になります。where to doを直訳すると「どこでする」という意味になりますが、それだけでは伝わりににくいので「どこでするべきか」と訳すことが多い。
where to doの使い方も、what to doやhow to doと同じように、「何を~するべきか」という訳し方の特徴と、疑問詞+不定詞のかたまりでとらえることがポイントです。
where to buyを言葉のかたまりとしてとらえて「どこで買うべきか」という意味になります。
不定詞は「to+動詞の原形」になるので、過去の出来事を言っている内容でもwhere to buyのbuyは動詞の原形になります。
<例文>
I decided where to start.
(私はどこで始めるべきか決めました。)
I didn’t know where to sit.
(私はどこに座るべきか分からなかった。)
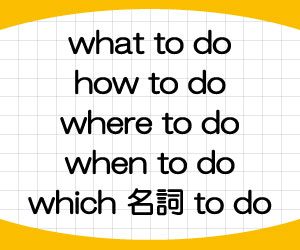
when to do「いつするべきか」
I don’t know when to go to her house.
私は彼女の家にいつ行くべきか分からない。
例文のwhen to goは、「いつ行くべきか」という意味になります。
「when to do」の基本的な使い方は、「what to do」「how to do」「where to do」と同じで、「疑問詞+to 動詞の原形」という形になります。
<例文>
I don’t know when to call him.
(私は彼にいつ電話するべきか分からない。)
She didn’t know when to start.
(彼女はいつ始めるべきか分からなかった。)
which(名詞)to do「どちらの(名詞)を~するべきか」
I didn’t know which way to go.
私はどちらの道に行くするべきか分からなかった。
「疑問詞+不定詞」の使い方は、疑問詞が変わっても基本的には同じなのですが、whichだけは使い方に少し違いがあります。
which to doは「どちらを~するべきか」という意味になりますが、whichの場合は名詞を間に挟むパターンがあって、which 名詞 to doで「どちらの名詞を~するべきか」という意味になります。
例文では、which way(名詞) to goで、「どちらの道に行くするべきか」という意味のかたまりになっています。
<例文>
I don’t know which one to choose.
(私はどちらを選ぶべきか分かりません。)
I don’t know which bus to take.
(私はどちらのバスに乗るべきか分かりません。)
Sponsored Links
おすすめの記事
shouldとmustの意味と使い方!should notとmust notの違いを解説!
中学英語の比較級を使った例文を紹介!Whichを使った比較表現の疑問文も解説!